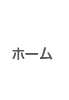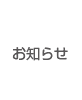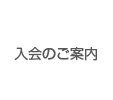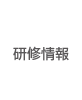ご挨拶
 この度、公益社団法人京都府介護支援専門員会の令和5・6年度期の会長に選任されました山下宣和です。
この度、公益社団法人京都府介護支援専門員会の令和5・6年度期の会長に選任されました山下宣和です。
私自身、力不足であることはよく承知しておりますが、諸先輩や他の役員、事務局の皆様のお力を借りて、精一杯務めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
介護保険制度が始まって、20年以上が経過し、介護支援専門員の認知度や期待度は年々高まっているように感じます。しかしながら、介護支援専門員の仕事の魅力は伝わっているのでしょうか。地域によっては、介護支援専門員の不足が顕著になっているところもあると聞きます。介護支援専門員の仕事は、要介護状態になった高齢者等の苦しみや不安を汲み取り、リスクの軽減、可能性を見極め、医療、介護、福祉、その他様々な人々や機関と連携し、その人らしい生活を支えていくものであって、とてもやりがいのある魅力ある仕事ではなかったでしょうか。
テレビなどで、「子どもたちが将来なりたい職業の人気ランキング」というのをみなさんご覧になられたことがありますか?最近では「ユーチューバー」なども人気があるそうです。私には、以前から夢があり、それは、「子どもたちが将来なりたい職業ランキング」に「ケアマネジャー」が入るぐらい認知され、社会的地位も認められるような職業になることを夢見ています。馬鹿らしいと思われるかも知れませんが、子どもたちに胸を張れる職業でありたいと思っています。
この会は、京都府に在住在勤の介護支援専門員で構成し、事業所はもちろん、市町村の枠を超えてつながり、さらには、近畿、日本中の介護支援専門員ともつながる組織です。一人でも多くの介護支援専門員の皆様に参加してほしいですし、要介護状態の人々やその人を支える家族の生活を支えるために頑張る介護支援専門員を応援していただきたいと願っています。
今、少子高齢化の真っ只中で、社会保障のあり方なども変化の時を迎えています。こういった時だからこそ、職業倫理、ケアマネジメントの技術をもっと高め、地域の介護の要として、医療と介護の連携のキーパーソンとして、信頼され、社会的な地位を獲得していく必要があると考えます。この会が、介護支援専門員をつなぎ、磨き合い、高めあう組織でありたいと考えています。
今後とも、皆様とともに前向きに歩んでいきましょう。お力添えをよろしくお願いいたします。